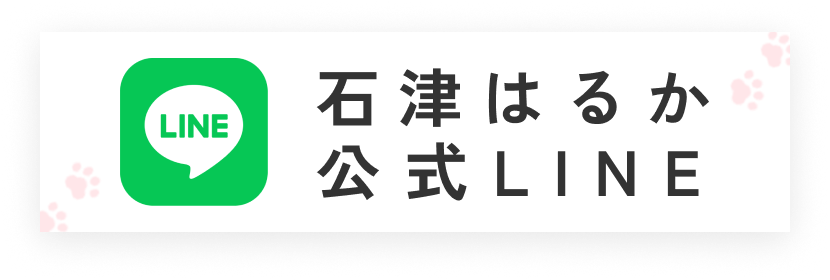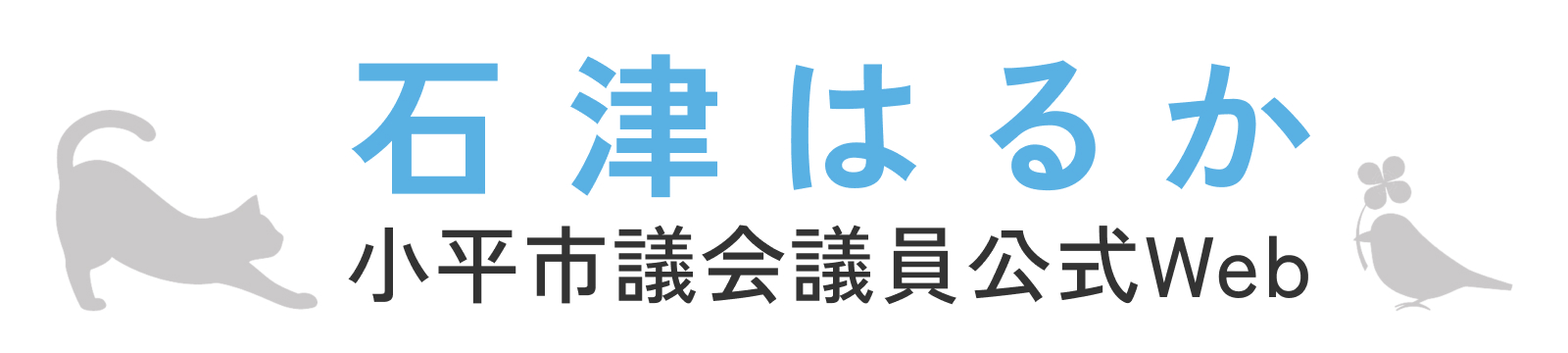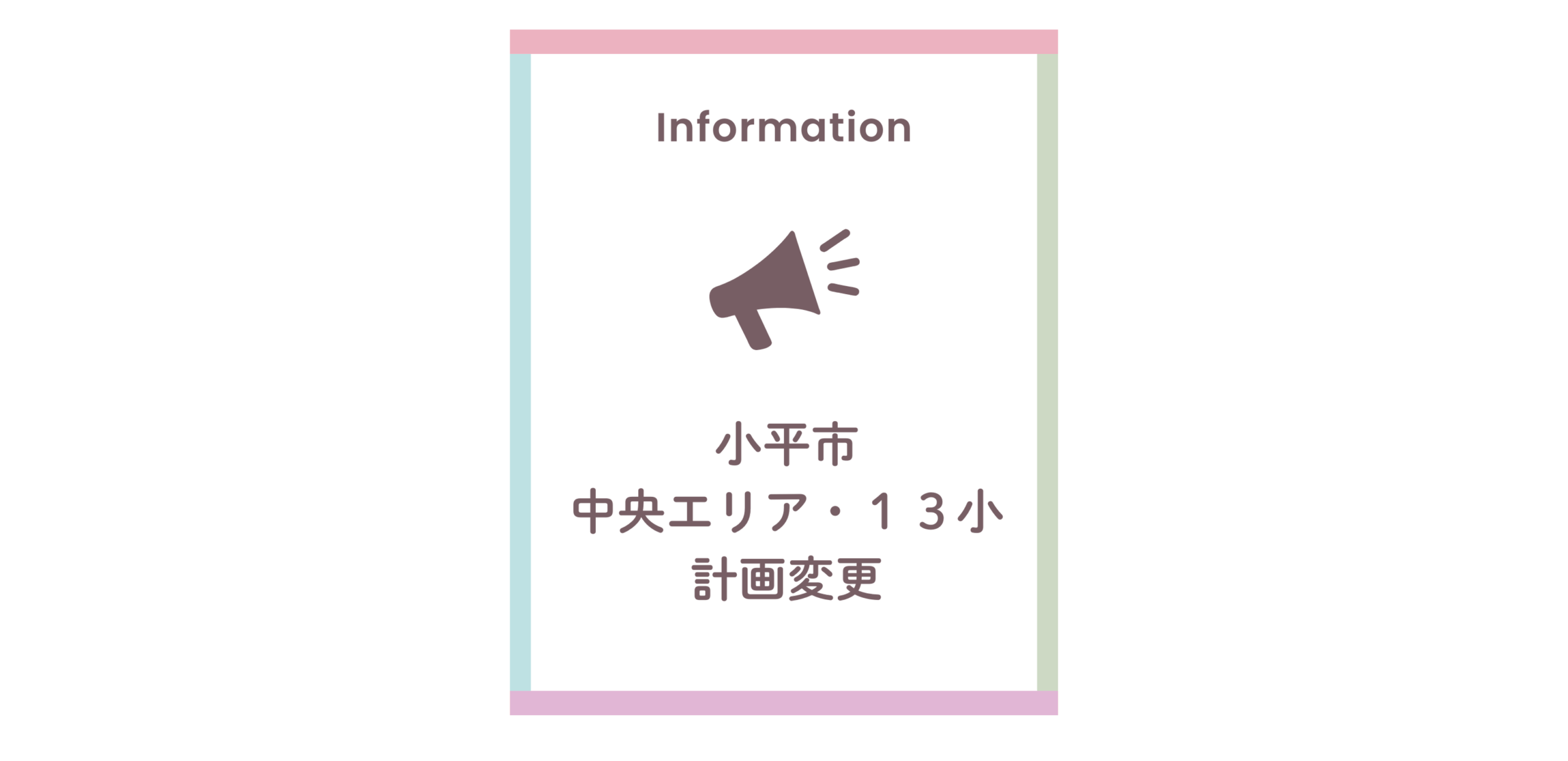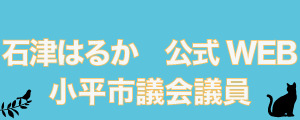本会議 一般質問① 飼い主のいない猫の課題解決で先進自治体に

6月定例会では一般質問を2問行いました。
■市民の納得感がある公共施設の在り方に向けて
■飼い主のいない猫の課題解決における先進自治体となるために
まずは「飼い主のいない猫」の課題について。
このテーマについては毎年取り上げており、たしかに数年前に比べてかなり施策は進んできました。
私が議員になったばかりの頃は「動物」の政策なんて・・・という雰囲気が。
議会での政策提言もありましたし、議会で話題になることも増えてきたことで
必要な政策であることが認知され始めた印象です。
特に公共施設での譲渡相談会開催は、他の自治体からも参考にされる先進事例でもあります。
■実現のレポートはこちら⇒https://ishizu-haruka.com/archives/2466

しかし今でもある地域で50匹以上の猫が出てきたり、多頭飼育崩壊が発生しています。
東京都からの補助も活用して毎年1,000万円規模の予算をつけられたのですがこれが来年度で終了するというタイミング。
補助期限が終わった後を見据えた体制整備が必要ということで質問・提言をしました。
まずは経済的な面について。
現時点での補助金の執行金額は約667万円、これが令和9年度からはゼロになるかもしれず
その負担はボランティアの皆さんにいくことになるので、今から仕組みづくりが必要だと提案したのが「ふるさと納税」の活用。


都内でも上記のように多くの自治体が「動物愛護」等の寄附金メニューをつくって寄付を募っています。
実際に犬・猫を飼うことは難しいけれど、不幸な動物を減らしたい、何かしたいという方は多くいらっしゃいます。
継続性や安定性の課題があると答弁がきましたので、では小平市には「選べる使い道」のメニューで様々な分野を設定しています。
基金として積み立てているものもあるので、中野区のように、ここにメニュー追加することぐらいは出来るだろうと提案しました。
答弁としては基金の設定等は難しいと・・・なぜチャレンジしないのか。
予算をかけずに出来ることからやっていこうと強く要望しました。
(左画像が「中野区」、右画像が「小平市」のふるさと納税、選べる使い道メニュー)


次に人材確保について。
ここで訴えたのは「保護猫関係のボランティアは趣味のボランティアとは違う点」です。
地域猫の管理・餌やり、猫の捕獲(⇒アライグマやハクビシンが捕獲機に入ると命がけです)
昼夜問わず入る相談対応、地域の方からのクレーム対応、譲渡会というイベント開催、広報業務。
これに加えて、日々命を預かっている責任と時間・労力・お金の負担・・・・・
清掃業務や施設管理業務は委託しているのに、これだけのことをやっても「無償ボランティア」なんです。
じゃあやらなきゃいい、という方もいますが、猫が増えてゴミが荒らされ、糞尿被害が出て環境問題になってもいいのか。
いきなり委託は難しくても、ボランティア・関わってくれる人を増やす努力はしていただきたいと要望しました。


ボランティアを増やすためのボランティア育成講座についてもぜひやっていただきたいと要望しました。
次に出口戦略、里親募集について。
これも今各団体さん任せになっていて、毎月譲渡会の開催はありますがなかなか新しい家族が決まらない子も。
20匹以上の猫を保護して疲弊していて、いつ自分が多頭飼育崩壊になるか心配するお声も何人からも聞いています。
福岡県筑紫野市では個人ボランティアの里親募集情報をHPに掲載されるなどしていて
行政の広報力と信頼性はこういうところにこそ使っていくべきと提案しました。
最後に行政のこの問題への向き合い方について。
担当の現場の職員の皆さんは本当によくやってくださっています。
でも市としての方向性や体制がそうではない、ボランティアがやるべきものだという感覚が強い印象です。
だからこそ今回の提案は3つ。
・市民の相談窓口は団体ではなく「小平市」であることの明確化。
(市で手に負えないものをボランティア団体にお手伝いいただいて解決するという体制をつくるべきことの提案)
・動物問題に関わる「専任職員」の配置。
・縦割りを解消し、特に福祉部門との連携を積極的に行うこと。
今課題となっている「高齢者とペット」の課題は今後どんどん増えていきます。
先日のセミナーで小平市として学んだことを実行に移さなければなりません。
また今回新たな取組として小平市が窓口となって「不要となったペット用品を募集」が始まりました!
小平市として、飼い主のいない猫の課題解決のための呼びかけ・積極的な取組を続けていただきたいと引き続き要望してまいります。