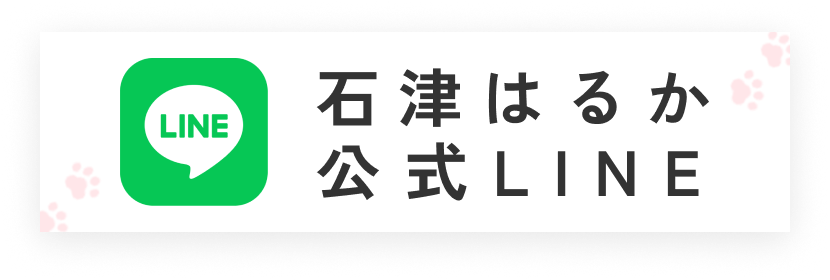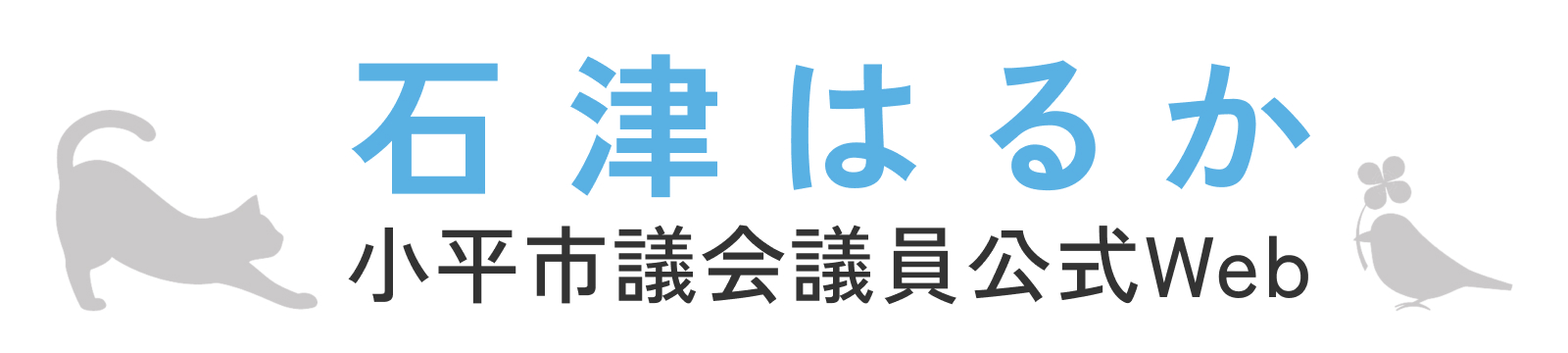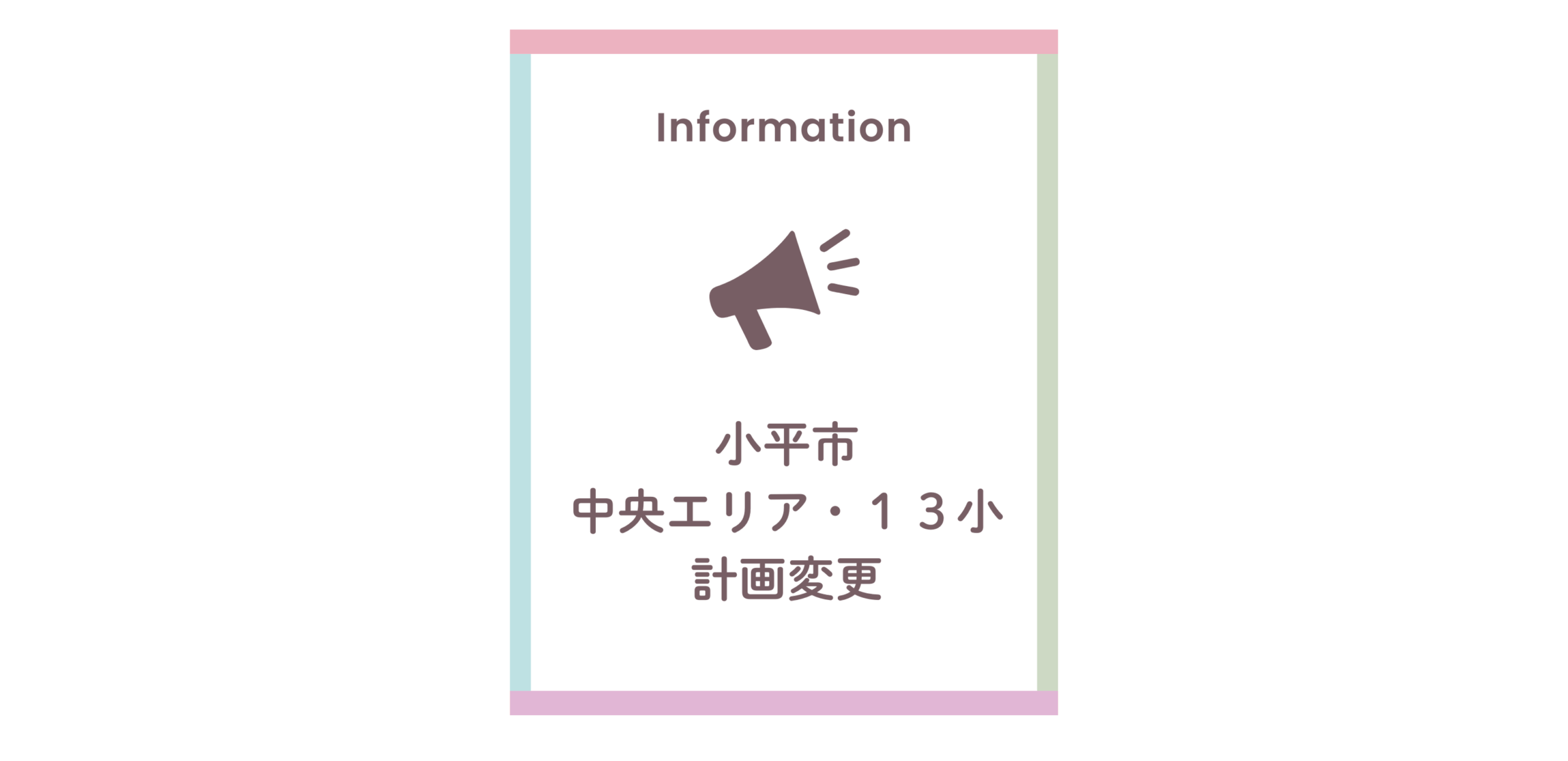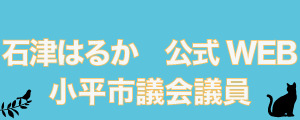多摩広域防災倉庫・立川地域防災センター視察
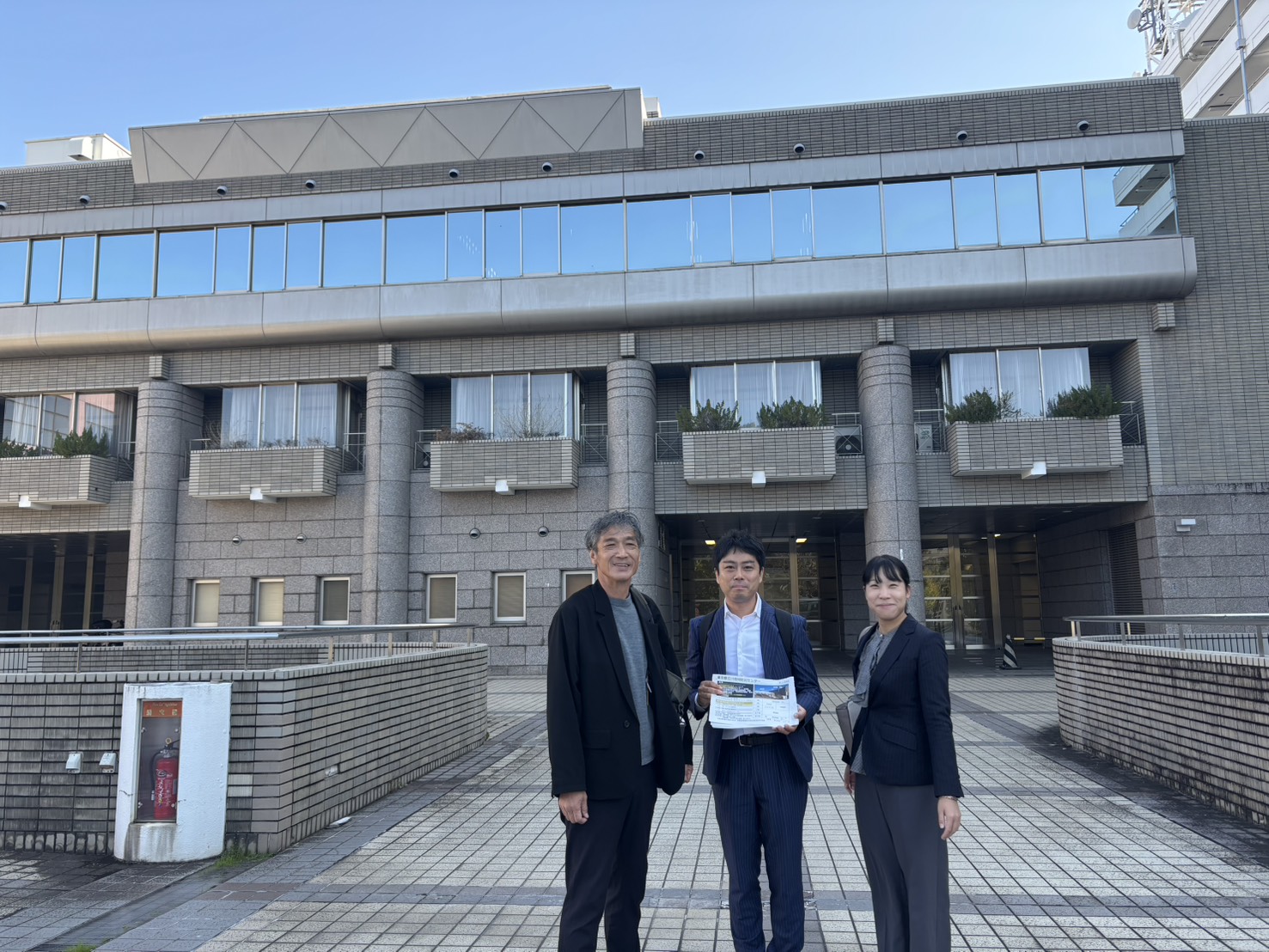
本日は松岡あつし都議にアレンジいただき、伊藤央市議とともに立川にある「東京都多摩広域防災倉庫」と
「東京都立川地域防災センター」内部を視察させていただきました。
今まで防災倉庫ができたことは知っていたのですが、
実際に中に入ったことはなく、実際の発災時の動きも深くは理解できていなかったので、
今回改めて詳しいご説明をいただいて学ばせていただきました。
※どちらの施設も内部写真のSNS公開はNGとのことなので、内容はレポートにて。
東京都多摩広域防災倉庫
ここは発災時に国や民間からの支援物資を受け入れて、各市区町村に輸送する「広域輸送基地」です。
都内には他に広域輸送のターミナルが4か所ありますが、それはどこも区部になるので、多摩地域ではここが中心になる見込み。
場所は立川駅から歩いて20分程度の場所にあります。

ここでは約200万人が3日間避難する想定で備蓄をしているとのこと(約1800万食分)
もともとは国のお米の備蓄倉庫であったところで、そこを活用して広大な倉庫で備蓄がされています。
1階は荷受け中心、2階以上が備蓄倉庫になっていました。
<東京都の主な備蓄物資>
①食料(クラッカー・アルファ化米等)
②調製粉乳(液体ミルク・粉ミルク等)
③生活必需品(毛布、敷物、紙おむつ等)
④その他(ブルーシート・段ボールベッド等)
小平市としても倉庫の一室を借りていて、
そこには大型の間仕切りや簡易トイレ、ブルーシート等が保管されていました。
発災後にすぐには使わない備蓄品が多い印象でしたが、災害時には借りている倉庫を空けなければならないとのことで、ここの運び出しには課題がありそうです。
多摩地域に防災倉庫があることは市内で対応しきれない時に安心ですが、災害時にどれだけスムーズに連携が取れるかが重要だと感じました。
東京都立川地域防災センター


防災倉庫から歩いて5分程のところにある都庁のバックアップ機能をもつ
防災センター内部も見せていただきました。
都の防災センターの代替施設として、災害対策室や一時避難室(体育館のような場所)、仮眠室、本部長室等もあり、自家発電も完備されていました。
実際にいざという時に情報が集まる場がどのようになっているかを学ばせていただきました。
視察に併設されるような形で隣には住宅棟があり常時50世帯が当番制で入っていただいていることも今回初めて知りました。
今回の視察を受けて、東京都と連携した防災訓練も必要ですし、発災時に具体的に何がどう動いていくのかを明確化しておく必要があることも再認識しました。
本日お世話になった皆さま、ありがとうございました!